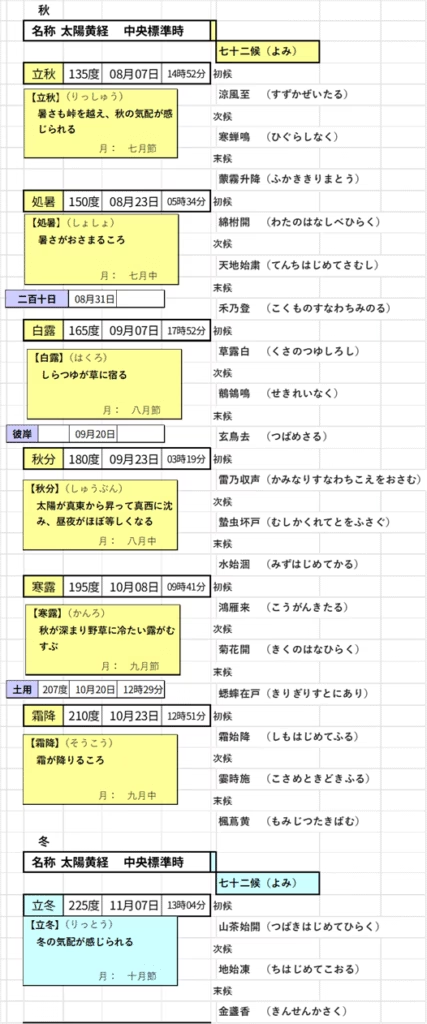目次
二十四節気|立秋(りっしゅう)暦のうえでは、秋のはじまり
「立秋(りっしゅう)」は、二十四節気のひとつで、秋の気配が立ちはじめるころを意味します。
2025年の立秋は、**8月7日(木)**です。ここから次の節気「処暑(しょしょ)」までの約15日間が、暦上の「立秋」にあたります。
でも、実際の気温は真夏のまっただなか。
立秋とは、体感と暦のあいだにある“季節のゆらぎ”を受けとめる節目とも言えるかもしれません。

【立秋】(りっしゅう)
暑さも峠を越え、
秋の気配が感じられる
月: 七月節 太陽黄経:135°
「秋」と言われても暑い──その理由は?
立秋のころ、日本列島の多くは猛暑のピーク。
連日の真夏日や熱帯夜、セミの合唱、夏祭りやお盆準備……どれをとっても「秋」という感じはしません。
それもそのはず。
二十四節気は太陽の動きに基づいた暦で、季節の区切りを「気配の変化」としてとらえます。
つまり立秋は、**暑さの“終わりが見え始める時期”**を告げるサインなのです。
朝夕の風がほんの少し軽くなり、空が高くなったように見える。
虫の声が変わり、日の入りが早くなる――そんな微かな変化を感じるための節気です。
立秋を境に変わること
立秋を過ぎると、歳時記や手紙の季語・時候の挨拶が「秋」に切り替わります。
- 「残暑お見舞い申し上げます」:立秋以降に使う表現
- 「初秋の候」「秋涼の候」などの季語表現
- 天気予報でも「秋雨前線」「秋晴れ」などの言葉が登場
つまり、文化のうえでは“秋の始まり”として扱われる日なのです。
自然と風景の変化
立秋のころには、目に見える風景にも変化が訪れます。
- 朝の空気が涼しく感じられる日がある
- 虫の声に、ヒグラシやコオロギが混じってくる
- 雲が巻雲や筋雲になり、空の色が淡くなる
- 山間や水辺では朝霧が立ち始める
セミが鳴く中でヒグラシの声が響いたり、日陰に入るとホッとする風が通ったり――
夏と秋が重なり合う瞬間が、立秋という節気の本質かもしれません。
🍇 暮らしと食、立秋のころ
立秋を迎えると、食卓にも少しずつ変化が見られます。
- 果物では、桃・ぶどう・梨・ブルーベリーが盛りへ
- 夏野菜(オクラ・枝豆・なす)に加え、初秋の京野菜や葉物も出回りはじめる
- 体調管理として、酸味や苦味を含む食材が重宝される時期
ふるさと納税の人気返礼品もこの時期は豊富です。
また、冷凍・冷蔵のスイーツや加工品など、**“残暑を涼しく乗りきるための贈り物”**としての需要も高まります。


行事と節目
立秋のころには、以下のような行事・風習が重なります。
- 七夕(旧暦/月遅れ):地域によっては8月7日ごろ開催
- お盆の準備:迎え火・仏壇の掃除・供物などが本格化
- 夏祭り・花火大会のピーク:多くの地域で最後の大規模行事が行われる
同時に、「夏休み後半」「帰省ラッシュ」「残暑疲れ」といった実感が強まるのもこの頃。
立秋は、単なる節目ではなく、生活のリズムを切り替えるタイミングでもあります。
ひとこと
「立秋」とは、“暑さの終わりを見つける季節”。
実際には暑くても、風の軽さ、虫の声、空の表情に、「次の季節が近づいている」ことを感じるための節気です。
忙しい日々のなか、ほんの少しだけ空を見上げてみてください。
そこに、まだ見ぬ秋の入り口が、静かに待っているかもしれません。
立秋の次…処暑

立秋のひとつ前…大暑

参考:令和7年立秋から立冬に至るタイムライン