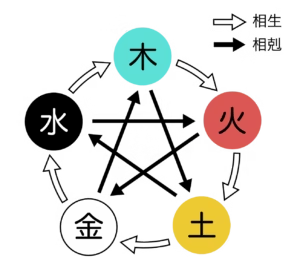目次
土用の入り
7月19日は、土用の入り。土用は、二十四節気とは別の「雑節」になっています。
夏の土用は、立秋前の18日間のことを言います。
実は、土用は、立春、立夏、立秋、立冬、それぞれの前の18日間、合わせると年間では72日になります。これには意味がありまして、それはこの後、出てきます。

【土用】(どよう)
夏の土用は立秋前の18日間のこと、
今年の土用の入りは7月19日
夏の土用 太陽黄経: 117°
四季の変わり目に現れる「土用」
「土用(どよう)」という言葉を聞いて、多くの人が思い浮かべるのは「土用の丑の日」「うなぎを食べる日」かもしれません。
ですが、本来の「土用」とは、季節の変わり目に訪れる“調整期間”のような時期で、春・夏・秋・冬すべてに存在しています。
暦上の定義
「土用」とは、二十四節気のうち“立春・立夏・立秋・立冬”の直前、約18〜19日間を指します。
つまり、「次の季節に切り替わる前の“仕上げ期間”」ともいえるのです。
具体的には、以下のようになります:
| 季節 | 土用の期間 | 切り替わり節気 |
|---|---|---|
| 冬の土用 | 1月17日頃~2月3日頃 | 立春 |
| 春の土用 | 4月17日頃~5月4日頃 | 立夏 |
| 夏の土用 | 7月19日頃~8月6日頃 | 立秋 |
| 秋の土用 | 10月20日頃~11月6日頃 | 立冬 |
特に有名なのが「夏の土用」で、真夏の暑さが極まる時期にあたります。
「土用の丑の日」とは?
「土用の丑の日(どようのうしのひ)」は、土用の期間中に訪れる“干支が丑の日”のこと。
2025年の夏の土用は、7月19日(土)~8月6日(水)。この間に1回または2回、丑の日があります。
「う」のつく食べ物(うなぎ、梅干し、うどん など)を食べて、夏の暑さを乗り切る――という風習があり、特にうなぎは、江戸時代の平賀源内の発案が有名です。
うなぎだけでなく、昔は「体に良いものを食べて備える」日でもあり、食養生の日としての側面がありました。
なぜ「土」? ― 土公神(どくしん)との関係
「土用」の“土”には、大地・地面の力が高まる時期という意味があります。
古代中国の五行思想では、春=木、夏=火、秋=金、冬=水、そしてそれらの間をつなぐ「土」が季節の調整役を担います。
この時期には「土公神(どくしん)」という土の神様が働くとされ、土を動かす作業(土木・植え替え・建築など)を避けるべきとされていました。
現在では信仰的な意味合いは薄れましたが、「土を休める」「身体を整える」時期としての考え方は、どこか理にかなっているとも言えます。
暮らしの知恵と土用
土用の時期には、昔ながらの暮らしの知恵が数多く残っています。
- 夏バテを防ぐ食事(うなぎ・梅干し・酢の物など)
- 大掃除や模様替えは避ける(特に土いじり)
- 静かに過ごし、秋に向けて体を整える
- 塩や炭を使って家の湿気や邪気を払う風習も
特に夏の土用は、湿度も高く体調を崩しやすい時期。
「一度整えて、次の季節を迎える」――そんな暮らしのリズムをつくる区切りとして、土用は現代にも活かせる知恵です。
ひとこと
土用は、単なる「丑の日」ではなく、季節の変わり目に生き方を見直す時期。
体調、暮らし、食事、心のあり方――あらためて整えるヒントが詰まっています。
現代の私たちにも、少し立ち止まって整える時間が必要かもしれません。
静かな「土の力」に耳をすませながら、次の季節を迎える準備をしてみませんか。
探求:【土用】※暦計算室で勉強してみました。
復習:雑節とは?
土用
- 季節に五行説?
| 土用 | 太陽黄経 | 月日 |
|---|---|---|
| 冬 | 297° | 1月17日ごろ |
| 春 | 27° | 4月17日ごろ |
| 夏 | 117° | 7月19日ごろ |
| 秋 | 207° | 10月20日ごろ |
- 土用を太陽黄経で決めるようになったのは → 明治二年暦
関連記事